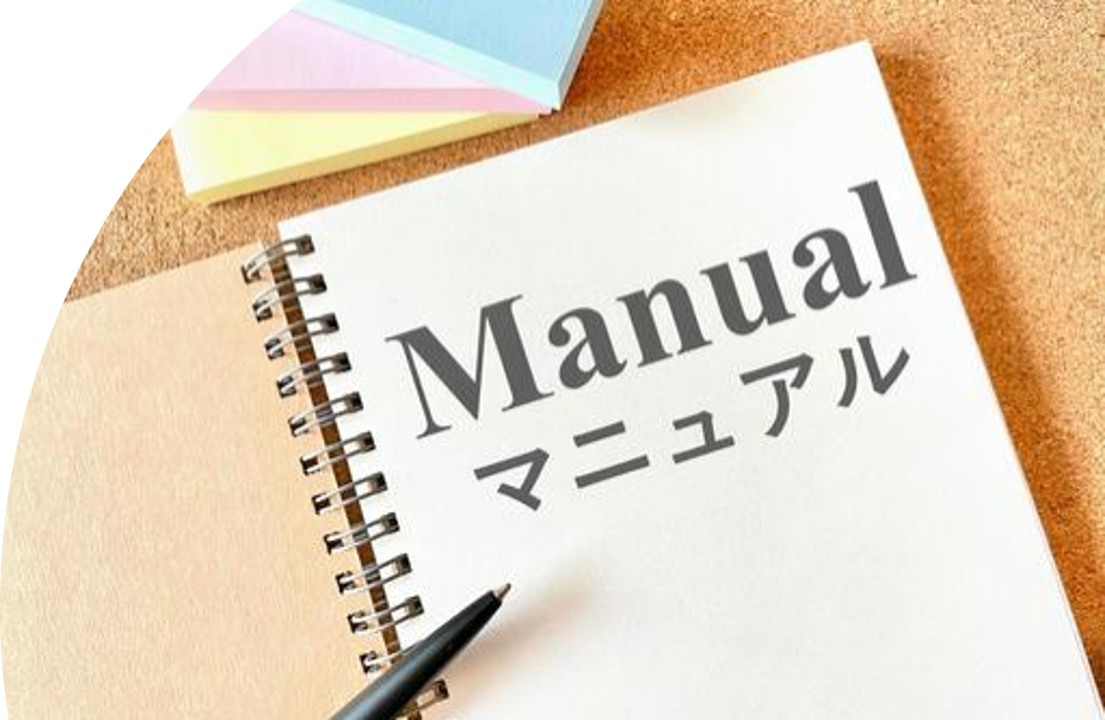教える側のスキル
2025年4月28日

ここ数年、私たちはコーチングスキルだけでなく、「ティーチングスキル」を深めるための研修にも力を入れています。その理由のひとつに、販売職の早期離職があります。クライアントから新人が店頭に立ち、販売の楽しさを経験する前に退職してしまう人が増えていると相談されたのです。
ヒアリングを重ね、何度も仮説を立てた結果、
「初動の指導方法」に問題があるのではないかという結論に達しました。
そこで、ティーチング研修では、
「動機づけ → 説明 → 理解度チェック」という指導の基本ステップを指導しています。
ティーチングに特化した研修を始めて5年になりますが、改めて気づいたことがあります。
動機づけがうまくできない人が、想像以上に多いということです。
実際、説明と動機づけが混ざってしまうケースがとても多いのです。
動機付けができない理由
では、なぜ動機づけができないのでしょうか?
最大の原因は、部下を指導するための「目標」が明確になっていないことにあります。
目標がハッキリしていないと、指導計画も立てられず、結果として動機づけの言葉も出てこないのです。
このように書くと、「目標はハッキリしている」と反論する方も多いです。
ですが、そのハッキリしている目標は、大目標「ゴール」だけを指していないでしょうか。
大目標だけでは、指導される側は最初に何をしていいか分かりません。目標が大きすぎるのです!
では、どうするべきか・・・
動機付けを成功させる
動機づけを成功させるには、まず「ゴール」を描くこと。
「いつまでに、どのようになってほしいか」という大目標を設定します。
そして、それを段階的にチャンクダウン=スモールステップをつくることが重要です。
イメージは、ダイエットや登山。
大目標:6ヶ月間で5㎏ダイエットする→4㎏→3㎏とスモールステップをつくりますよね。
登山も、最初から大きく険しい山を目指す人はいません。
先ずは、●●山から!とスモールステップをつくりますよね。
最初から一足飛びで大目標へは行かないのです。
スモールステップを作ることで、やるべきことが明確になり、動機づけするメッセージも明確にあります。
動機づけは、部下の集中力、やる気に直結する非常に重要なステップです。
目の前の指導が、本人にとってどのような意味があるのかを伝えることは、やる気を引き出す第一歩になります。単なるやり方の指示や注意喚起だけでは、モチベーションは高まりません。
新入社員が入社して、そろそろ1ヶ月。
多くの企業では配属先が決まる時期でしょう。
このタイミングで、**「動機づけ → 説明 → 理解度チェック」**という手順を意識して、しっかりと指導を行っていきましょう!
関連記事
SC協会主催「接客コンテスト関東甲信越大会」審査を終えて思うこと
SC協会主催「接客コンテスト関東甲信越大会」審査を終えて思うこと
少し前になりますが、SC協会主催「接客ロールプレイングコンテスト」の審査員を務めました。
今年は、飲食・食物販・サー...
現場新人マニュアルが必須な理由!
弊社も、先月からフォローアップ研修へ向けての準備が進んでいます。
仕事の覚え方や周囲との連携の深め方など...
接客ロールプレイングコンテストのフィードバックコメントへの思い
接客ロールプレイングコンテストのフィードバックコメントへの思い